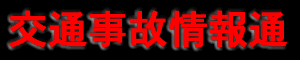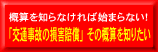|
�@���̂ɑ����A���ʉ@����������ǂ��P�K�����������A���ǂ��c���Ă��܂����ꍇ�ɂ́A��Q�҂͎����ӂɑ��Č��ǂ̔F��葱�����s���Ă������ƂɂȂ�܂��B�ꌾ�Ɍ��ǂƂ����Ă��A�A����ԂɂȂ��Ă��܂����A�S�g����Ⴢ��Ă��܂����A�ӎ���Q���c���Ă��܂����Ƃ������d�x�̂��̂���A���肪���т��A�Ǖ��̒ɂ݂��Ƃ�Ȃ��Ƃ�������r�I�y�x�̂��̂܂ł���̂ł����A�����͌��ǂ̓����Ƃ��ĂP������P�S���܂ł̊ԂŔF�肪�Ȃ���邱�ƂɂȂ�܂��B
����Q�ʓ����\
�@���Q�����Ƃ����ϓ_����́A���̌��ǂ̔F�肪����邩�ǂ����A�܂��������ł̔F�肪�Ȃ���邩�ŁA���̑��Q�����z���傫���قȂ��Ă��܂��B
�@���ǂ̔F��葱�����\�ɂȂ�̂́A���̌�U�����o�߂������_����ł���A���̓_�A��Q�҂ɏd�x�̌��ǂ��c���Ă��܂����ꍇ�ɂ́A��Q�҂����i�����I�ɉ������Ȃ��Ă��A�U�����o�߂����ӂ肩��A�ی���Ђ����ǂ̔F��Ɍ��������n�߂܂��B
�@�������A�����Œ��ӂ��Ăق����̂́A���ǂ̔F��Ɍ����ē��������Ƃ����̂́A�����܂ň�t�Ƃ̘b�����������Ƃɔ�Q�҂����肷�ׂ����̂ł���Ƃ������Ƃł��B
�@
�@�悭���ɂȂ�̂��A��t���܂����Â̕K�v������Ɗ����Ă��āA�Ǐ�͌Œ肵�Ă��Ȃ��Ƃ̔��f�����Ă���̂ɁA�ی���Ђ����ǂ̔F����}�����铮������t�y�є�Q�҂ɑ��Ă��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B
�@�m���ɁA�Ȃ�ׂ������i�K�ł̌��ǔF��́A�Ǐ��肵�Ă��Ȃ��i�K�Ō��ǐf�f�����쐬����邽�߁A�P�K�̓��e�ɂ���ẮA���̂��Ƃ����ǂ̔F��ɗL���ɓ����Ƃ������Ƃ��Ȃ��ɂ������炸�ł��B
�@�������A�t�ɂ��̑����i�K�ł̌��ǔF��Ɍ����Ă̓������A��Q�҂ɂƂ��āA�s���ɓ������Ƃ�����Ƃ������Ƃ��F�����Ă����K�v������ł��傤�B
�@�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���Q�����Ƃ����ϓ_����́A�ǏŒ肵���Ƃ������f�̂��ƈ�t�Ɍ��ǐf�f�����쐬���Ă���������_����A����܂ŕ⏞����Ă������Ô�͌��ǂƂ��Ă̕⏞�ɐ�ւ���Ă��܂����߂ɁA��Q�҂͂����������ŕ��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�i�����Ɍ����ƁA���ǂ̔F�肪���ۂɉ��肽�ꍇ�ɂ́A���̓_���܂߁A���ǂɑ���⏞�Ƃ��Ĕ������Ȃ���邱�ƂɂȂ�܂��j
�@���ɔ�r�I�y���Ȍ��ǁi���ɕڑł��Ȃǁj�̏ꍇ�̔�Q�҂́A���ǂ̔F��ɂ������āA�摜��̏������Ȃ����߂ɁA���ǂ̔F�肪�Ȃ���Ȃ��Ƃ������Ƃ���������܂����A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����Ƃ��ɁA��Q�҂Ƃ��ẮA�Ǐc���Ă���̂Œʉ@�͂��������A���Ô�̕⏞�͂Ȃ����߂ɁA�ʉ@���܂܂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��N���肦�܂��B
�@
�����̂��Ƃ���Q�҂ɂƂ��ėL���ɓ������ǂ����́A�����܂Ō��ʘ_�ł��̂ŁA��Q�҂Ƃ��ẮA���Â̕��j����ь��ǂ̔F��ɍۂ��ẮA��t�Ƃ̏\���Șb�������̏�ŐT�d�Ɍ��肷�ׂ��ł��B
�@
���Ȃ��Ƃ��A��t����u�܂��A�o�߂�����K�v������v�ƌ����Ă���ɂ�������炸�A�ی���Ђ���u���낻����ǂ̔F��Ƃ������Ƃœ����܂��傤�v�Ƌ}������āA���ǐf�f���̍쐬����t�Ɉ˗�����Ƃ������Ƃ͔������ق����悢�ł��傤�B
�@�����̖��͂��Ă����A���ǂ̓����ɂ��Ăł����A���ǂ̓����F��́A�����ӕی��́u���Q�ی������Z�o�@�\�v�Ƃ����Ƃ��낪�s���Ă��܂��B
�@
���̓����F��葱���Ɋւ��Ă͒ʏ�ی���Ђ���s���Ď葱�������邱�ƂɂȂ�܂����A����
�u���Q�ی������Z�o�@�\�v�ł̌��ǂ̔F��́A��{�I�ɏ��ʂɂ��R���ōs���邽�߂ɁA���Ƃ��Ĕ�Q�Ҏ���f���Ă��Ȃ��F�肪������邱�Ƃ�����܂��B
�@
���̏ꍇ�ɂ́A�u���Q�ی������Z�o�@�\�v�ɑ��A�K�ȓ������F�肪�������悤�Ɉًc�̐\�����Ă��s��Ȃ���Ȃ�܂��A���ً̈c�\���Ď葱���ɂ��Ă܂ł��ی���Ђ���s���čs���Ă����Ƃ͌���܂���B
�@��Q�҂Ƃ��ẮA�����̌��ǂ���̉������ɊY������̂��Ƃ������Ƃ����炩���ߓ��܂�����ŕی���Ђ̓������`�F�b�N���A�ꍇ�ɂ���ẮA����ًc�\���ĂɌ����ē����Ă���������Ȃ�܂���B
����Q�ʓ����\
�@
| ��Q�҂͉��Q�҂ɑ��Ă����琿���ł���̂��H |
�@�����ɓ����̔F�肪�I�������A���ɔ�Q�҂��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�u��̂����琿���ł���̂��v�Ƃ������Q�����̖��ł��B
�@���ǂ��c�鎖�̂̏ꍇ�ɔ�Q�҂������ł��鑹�Q���ڂ́A�ȉ��̂X�ł��B
1.����E���@��
�Q�D�ʉ@��ʔ�
�R�D���@�G��
�S�D�t�Y�Ō��p
�T�D�x�Ƒ��Q
�U�D���ʉ@�Ԏӗ�
�V�D���Lj편���v
�W�D���LjԎӗ�
�X�D���̑��̔�p
�@��L�̑��Q���ڂ̒��ŁA�P�D�`�U�D�܂ł́A�u���ǂ��c��Ȃ����́v�̏ꍇ�̑��Q���ڂƓ����ł��̂ŁA�u���ǂ��c�鎖�́v�ɂ�������L�̑��Q���ڂ́A�u�V�D���Lj편���v�v�u�W�D���LjԎӗ��v�Ȃ�тɁu�X�D���̑��̔�p�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���ł��u�V�D���ǂɂ��편���v�Ɓv�u�W�D���LjԎӗ��v�Ɋւ��ẮA���ɂ��̑��Q�����z�͌��ǂ̓����ɏ]���Čv�Z����܂��̂ŁA���̈Ӗ��ł��A��Q�҂ɂƂ��Ď����̌��ǂ��ǂ̓����ŔF�肳���̂��Ƃ������Ƃ͔��ɏd�v�Ȃ��ƂƂ����܂��B
�@
�@���āA�����Łu�W�D���LjԎӗ��v�Ɋւ��āA�ЂƂ��ӎ���������܂��B
�@���́u�W�D���LjԎӗ��v�Ƃ����̂́A��Q�҂��P�K�����Ēʉ@��������@�����肵���Ƃ��ɐ����ł���u���ʉ@�Ԏӗ��v�Ƃ͕ʂɐ����ł�����̂ł���Ƃ������������Г��ɓ���Ă����Ă��������B
�@���̓_�A�ی���Ђ̒��ɂ́A��Q�҂̖��m�ɂ�����ŁA�u���ʉ@�Ԏӗ��v��������Ĕ�Q�҂�[�������悤�Ƃ���҂����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�@�ی���ЃT�C�h����A��Ԏӗ��͂��̋��z�ł���ƌ����Ă��A���k���ɃT�C�����Ă��܂��O�ɁA���̈Ԏӗ��̒��ɂ�����ƌ��LjԎӗ����܂܂�Ă���̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��܂��͊m�F����悤�ɂ��܂��傤�B
�@�ȉ��A���ɂ��ꂼ��̑��Q�������ڂɂ��Ă̐��������܂����A�ȉ��L�q���Ă��鑹�Q�v�Z�̍����́A�u������ʎ��̑i�ׁ@���Q�����z�Z���v�A���Ȃ킿��ԍ��z�Ȋ�ł���ٔ�������Ƃɂ������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@ ���̍ٔ���ł̌v�Z�����邱�Ƃɂ���āA�u��Q�҂Ƃ��Ĉ�̂����琿���ł���̂��v�Ƃ������̏���z��m��Ɠ����ɁA���k�ɂ����đ���Ɂu��������Ȃ���Q�ҁv�Ƃ������b�e����\���Ȃ����Ƃ����ɏd�v�ɂȂ�܂��B
�Ԏӗ����܂߁A�����g�̃P�[�X�ɂ������̓I�ȑ��Q�����z��m�肽���Ƃ������́A���������ŊT�Z���Z�o�����Ă��������܂��̂ŁA���������炨�\�����݂��������B
1.����E���@��
�@���Ô�E���@��ɂ��Ă͕K�v�������Ȏ���S�z���F�߂��܂��B
�@�������A�ȉ��̂��̂ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł��B
�@���ʎ��g�p��
�����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ����A��t���×{��K�v�ƔF�߂��ꍇ�ȂǂŁA���Ï�L�����K�v������ꍇ�Ɍ���F�߂���B
�A�I���E�}�b�T�[�W��p
��t�̎w��������A���ÂɗL���Ȃ��̂��K�v���Ó��Ȕ͈͂��F�߂���B
�B����×{��
��t�̔F��Ǝw���̉��ɂ����̂̂݁A�K�v���Ó��Ȕ͈͂��F�߂���B
���@���R�̂��Ƃł����u�ߏ�f�Áv��K�v�ȏ�́u�Z���f�Áv�ɂ��Ă͎��̂Ƃ̈��ʊW�Ȃ��Ɣ��f����܂��B
|
�Q�D�ʉ@��ʔ�
�@ ��Q�҂��ʉ@�ɗv�����ʔ�́A�o�X�A�d�ԂȂǂ̌�ʋ@�ւɂ�闿���̌��x�Ő����ł��܂��B�������A���Q�̕��ʂ���݂ăo�X�A�d�ԂȂǂɂ��ʉ@������Ǝv����Ƃ���A�K���Ȍ����̌�ʋ@�ւ��Ȃ��ꍇ�ɂ̓^�N�V�[�����������ł��܂��B
�@ �x�o�������̂ɂ��Ă͗̎������͂��ׂĂƂ��Ă����A�̎������Ƃ�Ȃ����́i���Ƃ��o�X�A�d�Ԃ̉^���Ȃǁj�ɂ��Ă̓������c���Ă����悤�ɂ��Ă��������B
�@ ���̑�����ɂ��F�߂�ꂽ���̂Ƃ��Ă͈ȉ��̂��̂�����܂��B
�Ō�̂��߂̋ߐe�҂̌�ʔ�
���Ɨp�Ԃ̃K�\������A�������H�����A���ԗ���
���u�n�̏ꍇ�̏h����i�؍݂��K�v�ő����ł���ꍇ�j�A�������ƒ��y�ы��v��Ȃ�
�������̂��߂̌�ʔ�
|
�R�D���@�G��
�@ ��Q�҂����@�����ꍇ�́A���@���ɒʏ�K�v�ƂȂ���p�G�ݕi�i�Q��A�ߗށA���ʋ�A���莆�Ȃǂ̍w����j��h�{�⋋��i�����A�o�^�[�Ȃǂ̍w����j�E�ʐM��i�d�b�A�X�֑�Ȃǁj�E������i�V���G����A���W�I�E�e���r���ؗ��Ȃǁj���܂Ƃ߂āA1���ɂ�
1,500�~���x���G��Ƃ��Đ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���̕��̐����ɂ�����̎����͕s�v�ł����A��z����ꍇ�ł��Љ�ʔO��A�K�v���Ó��Ȕ͈͂ł���ΔF�߂���̂ŁA���ׂ�������`�ŗ̎����͕ۊǂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�i�P�j���p�i�G�ݔ�i�Q��A�ߗށA���ʋ�A���莆�Ȃǂ̍w����j
�i�Q�j�h�{�⋋��i�����A�o�^�[�Ȃǂ̍w����j
�i�R�j�ʐM��i�d�b�A�X�֑�Ȃǁj
�i�S�j������i�V���G����A���W�I�E�e���r���ؗ��Ȃǁj
|
�S�D�t�Y�Ō��p
�@ ��t�̎w���A�̕��ʁA���x�A��Q�҂̔N��Ȃǂ���݂āA�t�Y���K�v�ł���A��Q�҂͕t�Y�Ō��p�ɂ��Đ����ł��܂��B�����琿���ł��邩�ɂ��ẮA�ʉ@�����@���A�܂��E�ƕt�Y�l���ߐe�҂��t�Y�����̂��ɂ���Ĉ���Ă��܂��B
�i�P�j�ʉ@�̏ꍇ
�@�E�ƕt�Y�l�̏ꍇ�E�E�E�E�E�E�E�E�E�S�z�������\
�@�c���A�V�l�A�g�̏�Q�҂Ȃǂɋߐe�҂��t�Y�����ꍇ�E�E�E 1���ɂ��R�O�O�O�~�`�S�O�O�O�~�i�Q�j���@�̏ꍇ
�@ �E�ƕt�Y�l�̏ꍇ�E�E�E�E�E�E�E�E�E�S�z�������\
�@ �ߐe�҂��t�Y�����ꍇ�E�E�E�E�E�E1���ɂ��T�T�O�O�~�`�V�O�O�O�~
|
�T�D�x�Ƒ��Q
�@ ��ʎ��̂ŁA��Q�҂��P�K�����Ēʉ@�E���@�������Ԓ��Ɏd�����x�݁A�������������ꍇ�ɁA���̌������𐿋����邱�Ƃ��ł��܂��B���̋x�Ƒ��Q�́A�����܂ł����ۂ̌������ɑ���⏞�ł��邽�߁A���E�ł������ꍇ�Ȃǂ�
���ۂɎ����͌������Ă��Ȃ����ߐ������邱�Ƃ��ł��܂���B�������A��Ǝ�w��A�E�������̎��Ǝ҂Ȃǂ̏ꍇ�ɂ́A���ړI�Ȏ����̌����͂Ȃ��̂ł����A���Q�͐����Ă���̂Ő������邱�Ƃ��\�ł��B
�@��Ј��̋x�Ƒ��Q�v�Z��
�@�x�Ƒ��Q�̌v�Z���́A
�@�u(�P��������̕��ώ����z�~�x�Ɠ���)�|(�ꕔ�x���z)�v�ł��B
�@1��������̕��ώ����z�́A���̑O�R�����Ԃ̎x���z���X�O���ŎZ�o���܂��B�x���z�ɂ́A��{���^�̂ق��c�Ƒ�Ȃǂ̏��蓖���܂܂�܂��i�Љ�ی����⏊���ōT���O�̊z�j�B
�@���ɁA���̊z�ɋx�Ɠ����i���Γ����j�������܂��B�x�Ɠ����i���Γ����j�ɂ́A��Q�҂��L���x�ɂ��g���Ďd�����x���ɂ�������܂��B
�@�ʏ�͂���ŎZ�o���ꂽ�z���x�Ƒ��Q�ƂȂ�̂ł����A�������̂��o�Γr���ɋN�����ȂǂŁA���Ȃ����J�Ђ��狋���̉��������x������Ă����肵���Ƃ��ɂ́A���̕��͈����Ȃ���Ȃ炸�A���̈ꕔ�x���z���������c�肪�x�Ƒ��Q�ƂȂ�킯�ł��B
��@�T�����[�}���`����@�@
�����R�U���~�i�Љ�ی����⏊���ōT���O�̊z�j
���Γ����͂P�T���i���̂����R���Ԃ͗L���x�ɂ��g�p�j
�J�Ђ���̎x���͂Ȃ�
�@1��������̕��ώ����z�P�O�W���~���X�O�����P�Q�O�O�O�~
�A�x�Ƒ��Q�z�P�Q�O�O�O�~�~�P�T�����P�W���~
�Ȃ��A��Ј��́A��Ђ̔��s����u�x�Ƒ��Q�ؖ����v�u�����[�v�Ȃǂɂ���Ď����z�A�x�Ɠ������ؖ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�A���c�Ǝ҂̋x�Ƒ��Q�v�Z��
�@�x�Ƒ��Q�̌v�Z���́A
�@�u(�P��������̕��ώ����z�~�x�Ɠ���)�|(�ꕔ�����z)�v�ł��B
�@1��������̕��ώ����z�́A���̑O�N�̎����z(�����Ő\�������z)���R�U�T�ŎZ�o���܂��B�����ɂ��Ắu�m��\�����v��u�����ؖ����v�����ƂɌv�Z���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���̊z�ɋx�Ɠ��������������z���x�Ƒ��Q�̊z�ƂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A���Ǝ�̋x�Ƃɂ���āA���Ǝ��̂��x�܂���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�X�܁E�������̉ƒ���A�]�ƈ��̋����A�ی����Ȃǂ̌Œ��������ł���ꍇ������܂��B
�B��w�̋x�Ƒ��Q�v�Z��
�@��w�̏ꍇ�̋x�Ƒ��Q�̌v�Z���́A
�@�u�����Z���T�X�̏��q���ϒ����~�x�Ɠ����v�Ōv�Z���܂��B
�@�Ǝ��̑Ή��͎Z�肪����Ȃ��ߒ����Z���T�X�Ƃ����A�J���Ȃ��o���Ă��鏗�q�̑S�N��̕��ϒ�������ɂ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�����Z���T�X�ɂ��A���q�̑S�N��̕��ϒ����́A�R�T�Q���Q�S�O�O�~�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA������R�U�T���Ŋ���ƁA1��������̕��ϒ����͂X�U�T�O�~�ƂȂ�܂��B
�@����ɓ��@��ʉ@�̂��߂ɉƎ����x��ł������Ԃ�������A��w�̋x�Ƒ��Q���Z�o�ł��܂��B�i�������A����̓��e�ɂ���Ă͑S�z���F�߂�ꂸ�A��w�Ƃ��Ă̘J���\�͂�r�������Ƃ����͈͂ł̔F��ƂȂ�ꍇ������܂��B�j
�@
�d��������w�̏ꍇ�́A���̎�w�̋x�Ƒ��Q�Ǝ������̂����ꂩ�������𐿋����܂��傤�B
�@�Ȃ��A�Ǝ����Ɛ��w�Ȃǂɗ��܂Ȃ�������Ȃ������ꍇ�ɂ́A�x�Ƒ��Q�ɂ����ĉƐ��w�Ɏx���������z�𐿋��ł��܂��B |
�U�D���ʉ@�Ԏӗ�
�@ �Ԏӗ��̊z�Ƃ����̂͂�����x��z������Ă���A���̊�͑傫�������ĂR��ނ���܂��B
�@���z���Ⴂ���̂��珇�Ɂu�����ӊ�v�u�C�ӕی���v�u���٘A��i�ٔ���j�v������܂��B�ڈ��������A�����ӊ���P�Ƃ���ƔC�ӕی���P�D�T�{�A�ٔ�����Q�{�Ƃ������Ƃ���ŁA�ǂ̊�ňԎӗ����Z�肷�邩�ɂ���Ă��Ȃ�̍����o�Ă��܂��B�i�u���٘A��v�̈Ԏӗ��z�ɂ��ẮA���������Q�Ƃ��Ă��������B�j
�@�ی���Ђ́A�u�Ԏӗ��͂��̊z������ł��B�v�Ȃǂƌ����āA��ԒႢ��ł��鎩���ӊ����b�ɑ����������������z����Ă���̂���ʓI�ł��B
�@�������A�����ӊ�Ƃ����̂́A�����܂ł����ɂ��Œ�⏞�ł�����A��Q�҂͂���Ŕ[�����Ă͂����܂���B
�@�u���ۂɂǂ̂�����Ŏ��k���Ȃ���邩�v�Ƃ������Ƃɂ��Ăł����A���������ł̉�������Q�l�ɂ݂܂��ƁA��Q�҂����k�̔��e�ł̉������̂��ޏꍇ�ɂ́A�u�C�ӕی���v�Ɓu���٘A��i�ٔ���j�v�̒��Ԃ̋��z�Ŏ��k����P�[�X���قƂ�ǂł��B
�i���Q�̌v�Z���@���悭�킩��Ȃ��ꍇ�ɂ́��u���Q�T�Z�T�[�r�X�v�������p���������B�j
�V�D����Q�ɂ��편���v
�@ ��Q�҂̃P�K�����Â̍b��Ȃ��A��������ȏ�͎��Â��p�����Ă��悭�Ȃ�Ȃ��Ƃ�����Ԃ̂��Ƃ��u�Ǐ�Œ�v�Ƃ����A���̏�Ԃɓ���Ɣ�Q�҂͉��Q�҂ɑ��Č��ǂɂ��편���v�i���̂��Ȃ���Ζ{���͓���ꂽ�ł��낤��Q�҂̎����j�������ł���悤�ɂȂ�܂��B�A���A���̑O��Ƃ��āA����Q�����ɊY��������x�̌��ǂł���K�v������܂��̂ŁA��Q�҂́A�u�Ǐ�Œ�v�̒i�K�Ō���Q�����̔F��葱���邱�ƂɂȂ�܂��B
�편���v�̌v�Z���́A
�@�N���~�A�J���\�͑r�����~�B�W���ł��B
�@ �܂��N���z���m�肵�Ă��������B
�������ؖ��ł���l�̏ꍇ�ɂ́A����Q�m���܂��͎��̑O1�N�Ԃ̎����i�����ōT���O�̂��́j�ƂȂ�A�������ؖ��ł��Ȃ��l�i�c����18�Ζ����̊w�����w�A���E�҂Ȃǁj�̏ꍇ�ɂ͒����Z���T�X�̒j���ʑS�N��ϒ����Ɋ�Â����z�Ōv�Z���܂��B�����Z���T�X�ɂ��ẮA���������Q�Ƃ��Ă��������B
�A ���Ɍ��ǂ��������ɂ�����̂��ƁA����ɑΉ������J���\�͑r�����ׂ܂��B����Q�ʓ����\�����������Q�Ƃ��Ă��������B
�B �Ō�ɌW���ׂ܂��B�W�������������Q�Ƃ��Ă��������B
��P�@�T�����[�}���`����@�@�R�T�E��Ј��E�����R�T���~�E�{�[�i�X�N�ԂP�O�O���~
�@�@�@ ����̎��̂ɂ���āA�E�ڂ���������
�@�N���@�R�T���~�~�P�Q�����{�{�[�i�X�P�O�O���~���T�Q�O���~
�A����Q�@�W���E�J���\�͑r�����S�T��
�B�W���@ �P�T�D�W�O�R
���Lj편���v�@�T,�Q�O�O,�O�O�O�~�~�O�D�S�T�~�P�T�D�W�O�R���R�U,�X�V�X,�O�Q�O�~
��Q�@��wB����@�Q�T�E��w
�@�@����̎��̂ɂ���āA�����g�t���ɂȂ���
�@ �����Z���T�X�ɂ��A�N���@�R,�T�Q�Q,�S�O�O�~
�A ����Q�@�P���E�J���\�͑r�����P�O�O��
�B �W���@�P�V�D�S�Q�R
���Lj편���v�@�R,�T�Q�Q,�S�O�O�~�~�P�D�O�O�~�P�V�D�S�Q�R���U�P,�R�V�O,�V�V�T�~
�@��{�I�ɂ́A�편���v�̌v�Z�͈ȏ�̌v�Z���ŋ��߂���̂ł����A�ނ������ǂȂǂ̌��ǂł́A�편���v���Q�N���x�����F�߂��Ȃ����Ƃ�����܂��B
�@���ǎ��Ă̏ꍇ�ɂ́A�����̔F��⑹�Q�z�̊m��Ȃǐ��I�Ȓm�����s���ł��̂ŁA�����ɂ������ẮA�K�����Ƃ̎�����悤�ɂ��Ă��������B
�����g�̃P�[�X�ɂ����鑹�Q�����z�̊T�Z��m�肽���Ƃ������́A���������ŊT�Z���Z�o�����Ă��������܂��̂ŁA���������炨�\�����݂��������B
|
�W�D����Q�ɑ���Ԏӗ�
�@���āA���Q���̈Ԏӗ��ł���u���ʉ@�Ԏӗ��v�Ƃ͕ʂɁA��Q�҂����ǂ��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�u���ǂ̈Ԏӗ��v���ʓr�����ł���Ƃ������Ƃɂ��ẮA�O�q���܂����B���ʉ@�Ԏӗ��ɂ��ẮA���ʉ@�̓����A���Ԃ���v�Z�����܂����A���LjԎӗ��ɂ��ẮA����Q�̓����ɂ���Ă�����x��z��������Ă��܂��B
�@���ʉ@�Ԏӗ��Ɠ��l�A���LjԎӗ��ɂ��R�̊������A��Q�҂��ٔ���]�܂��A���k�ʼn�������ꍇ�ɂ́A�u�C�ӕی���v�Ɓu���٘A��i�ٔ���j�v�̊Ԃ̋��z�ł܂Ƃ܂��Ă���̂���ʓI�ł��B
�@�����ł͍ٔ�����ڂ��Ă����܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������B
| ���� |
���z
|
| 1 |
2600�`3000���~ |
| 2 |
2200�`2600���~ |
| 3 |
1800�`2200���~ |
| 4 |
1500�`1800���~ |
| 5 |
1300�`1500���~ |
| 6 |
1100�`1300���~ |
| 7 |
900�`1100���~ |
| 8 |
750�`870���~ |
| 9 |
750�`870���~ |
| 10 |
480�`570���~ |
| 11 |
360�`430���~ |
| 12 |
250�`300���~ |
| 13 |
160�`190���~ |
| 14 |
90�`120���~ |
�X�D���̑��̔�p
�@ ���ǂ��c���Ă��܂����ꍇ�ɂ́A���̌��ǂɂ���ď���������ł��낤�o��ɂ��Ă��A�������邱�Ƃ��\�ł��B
�@���Ƃ��A��Q�҂ɍ��x�̌���Q���c�����ꍇ�A����ł̐������s���R�ɂȂ�Ȃ��悤���C��g�C���A�ԂȂǂ����������肵�Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A���K�l�A�⒮��Ȃlj��N�������甃���ւ��Ȃ�������Ȃ����̂ɂ��Ă͂��̔����ւ���p�ɂ��Ă��A�����_�Ő������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����_�łƂ������̂́A�{���Ȃ珫�������ւ�����̂ɂ��Ă͂��̎��_�Ő������ׂ����̂ł����A����͑�ςȂ̂ŁA�����_�Ŕ����ւ���z�肵�Đ������Ă������Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B�������A�����������{���Ȃ珫���ɐ������ׂ����̂������_�Ő�������Ƃ������ނ̂��̂ɂ��ẮA���ԗ����i�@�藘���T���j���T�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
| ���Ȃǂ̍w���� |
�Ԉ֎q�A�⒮��A�`���A���ꎕ�A���K�l�A�ӓ����Ȃ� |
| �Ɖ��E�����ԂȂǂ̉����� |
�Ԉ֎q�ł̐������\�Ȃ悤�ɉƂ̒i�����Ȃ����E�ƒ�p�G���x�[�^�[������Ȃ� |
�� �����̎��Ô�E��p��E�t�Y���Ō엿�Ȃǂɂ��ẮA�����ɕK�v�s���Ȃ��̂łȂ��ƌ����͐����ł��܂��A���������ǂ̕��ʁE�����E���x����ꍇ�ɂ���Ă͐����ł��܂��B
| �Ȃ�ׂ������i�K�ŏ؋����W���I |
�@��Q�҂����̌�ɋ~�}�ԂŔ������ꂽ�ꍇ��A���̌�A���炭�ӎ����Ȃ������Ƃ����悤�ȏꍇ�ȂǂɁA���Q�ґ��Ɣ�Q�ґ��̊Ԃł̎��̔����ɂ��Ă̈ӌ����H������Ă���Ƃ������Ƃ�����܂��B
�@���S���̂̏ꍇ�ɁA��Q�҂Ɉ���I�ɉߎ��������t�����A���Q�����z���傫�����炳��Ă��܂�����A��Q�҂ɑS�ʓI�ȉߎ�������Ƃ����K���������Ȃ���Ȃ��Ƃ����u���l�Ɍ��Ȃ��v�̈������Ȃ���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��悭���ɂȂ�܂����A���̖��́A���S���̂Ɍ���ꂽ���̂ł͂���܂���B
�@
���ǎ��Ăł��A���ɁA��Q�҂����̌�ɋ~�}�ԂŔ������ꂽ�ꍇ��A���̌サ�炭�ӎ����Ȃ������Ƃ����悤�ȏꍇ�A��Q�҂ɏd�x�̌��ǂ��c���Q�҂��،��ł��Ȃ��ꍇ�Ȃǂɂ�����Ɠ��l�̂��Ƃ��N���肦�܂��B
�@���Q�҂Ƃ����̂́A�ӎ��A���ӎ��͕ʂɂ��āA���X�ɂ��Ď����ɗL���ȏ،�������X��������܂��B�������̂悤�Ȗ��Ɋׂ����Ƃ��ɁA��Q�ґ�������̌������ɑR�ł����i�Ƃ����́A�����̎咣�𗠕t���Ă����؋���������܂���̂ŁA��Q�҂܂��͔�Q�҂̉Ƒ��́A���̂��Ƃ�O���ɂ����āA�Ȃ�ׂ������i�K�œƎ��ɏ؋����W�����Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�@���̓_�A�x�@���쐬����������������́A�����܂ʼn��Q�҂̌Y�������̂��߂̂��̂ł���A���ɁA���̒����͉��Q�҂̋��q�ɂ���Ęc�߂��Ă��܂����Ƃ�����̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
| �؋��͋�̓I�ɉ����ǂ�����ďW�߂�悢�H |
�@�\�ł���Όx�@�̎��������ɗ�����A�ڌ��҂�����A�ڌ��҂��玖�̂̏ɂ��Ă̏���悤�ɂ��Ă��������B���̌x�@���쐬����������������͂����܂ʼn��Q�҂̌Y�������̂��߂ɍ쐬�������̂ł����A���̒����̋L�ڎ������A��ɔ�Q�҂�����Q�҂ɑ��ĂȂ���閯����̑��Q���������ɂ����Ă��A�d�v�ȏ��ނɂȂ邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B
�@ �ł������A������Ƃ����������쐬�����悤�����K�v������܂��B�܂��x�@�̒����Ƃ͕ʂɁA��Q�ґ��ł��Ǝ��Ɏ��̂̔����ɂ��ď؋��ƂȂ肤����̂ɂ��Ďʐ^���B������A�}�ʂ��쐬����Ȃ肵�ċL�^���c���悤�ɂ��Ă��������B
�@���̒���ɂ́A���̎��̂��ǂ̂悤�ɂ��ċN�������̂��ɂ��Ă̏؋�����R�c���Ă��܂��B�����ł́A�x�@���ʏ�A�������������ɋL�ڂ���؋��ނɂ��āA���̂̔����𐄎@���邤���ł͂ǂ̏؋����ǂ̂悤�ɖ𗧂̂��ɂ��Đ������܂��B���i�K�Ŕ�Q�҂Ƃ��ēƎ��Ɏ��W�ł�����̂͌����Ă��邩������܂��A�ł������̏؋������W����悤�ɂ��Ă��������B
�@�؋��Ƃ́A�ڌ��ҁA�����A�K���X�Ȃǂ̔j�ЁA���̎ԗ��A���H��Ɏc�����^�C���̍��ՂȂǂ̂��Ƃł��B
�E�E�E����ɂ�����A���O�ƘA�����K�������܂��B�ڌ��҂͌ォ��T���o���͔̂��ɍ���ł��B�܂��A�ڌ��҂̏،��́A���Q�W�̂Ȃ���O�҂̂��̂ł�����A�؋��\�͂̓_�Ŕ��ɏd�v�ł��B
�E�E�E�����̈ʒu�ɂ���āA��Q�ҁi���Q�ҁj�����̂ɂ���Ăǂ���̕����ɔ����A���̌���������܂łǂ̏ꏊ�ɂ����̂��̎肪����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�ʐ^�Ɏ��߂�ƂƂ��ɁA�ʒu��}�ʂɋL�����܂��B
�E�E�E���̂ɂ���ĎԂ̃K���X�Ȃǂ����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̃K���X�����̌�ǂ̈ʒu�ɔ��ł����̂��ɂ���ďՓˈʒu���ǂ��ł������̂��̎肪����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�ʐ^�Ɏ��߂�ƂƂ��ɁA�ʒu��}�ʂɋL�����܂��B
�E�E�E���̎ԗ��̔j�����ʂƒ��x�A���̌�̎��̎ԗ��̒�~�ʒu�ɂ��A�ǂ̂悤�ȏŋN���������̂Ȃ̂���c������傫�Ȏ肪����ƂȂ�܂��B�ʐ^�Ɏ��߂�ƂƂ��ɁA��~�ʒu��}�ʂɋL�����܂��B���̎ԗ��̎ʐ^���B��ꍇ�ɂ́A�Փˉӏ��𐳖ʂ���B�邾���ł͂Ȃ��A�����猩�Ăǂ̒��x�̉���Ȃ̂��i�ł�����W���[���ʼn��݂��v�����Ȃ���B�e����j���킩��悤�ɎB�e����悤�ɂ��Ă��������B�傫�ȉ��݂����łȂ��A�����ȏ�������Ƃ��͂��������ׂă��W���[�Ōv�����Ȃ���B�e���Ă��������B�i�ł���ΐڎʂ��Ă��������j�E�E�E�X���b�v���A�����荭�Ȃǃ^�C���̍��ՁA�������i�Փ˂ɂ��ԑ̂̋��������ɂ���ĘH�ʂɂ���ꂽ���̂��Ɓj�A�I�C�����ȂǘH�ʏ�Ɏc���Ă���؋��ɂ��A���̂̔����A�X�s�[�h����m��肪����ɂȂ�܂��B�����͎ʐ^�Ɏ��߂�ƂƂ��Ƀ^�C���̍��Ղɂ��ẮA�����[�g������̂��v�����A�}�ʂɋL�����܂��B
�E�E�E����̐i�s�����A��Q�҂̐i�s�������ꂼ��̓��H�ɗ����A���̌�������Ɍ������ĎB�e���܂��B���̓����҂̎��̑O�̎������玖�̌��ꂪ�ǂ̂悤�ɉf�����̂����킩��悤�ɎB�e���܂��B
�E�E�E�V��i���H�̎����A�����A�ϐ�j�⓹�H�̋L�^�i�傫�Ȏ��̂���������Ƃ��̓��H�ɂ͑��x�K�����Ȃ��ꂽ��A�X�����ݒu���ꂽ��A���C���Ȃ��ꂽ�肵�ē��H��������Ă��܂����Ƃ�����܂��j�A���H�W���i�ō����x�A����ԋ֎~�A��U��~�A�ljz�֎~�A���f�����A�Z���^�[���C���A�M���@�A�K�[�h���[���A�������Ȃǁj������Ύʐ^�Ɏ��߈ʒu���L�^���A���Ԏԗ�������i���o�[�����L�^����悤�ɂ��܂��B
| ���Q�҂ɂ͂ǂ̂悤�Ȑ��ق������̂��H |
��ʎ��̂Ől�ɃP�K�킹�Ă��܂������Q�҂́A�傫�������ĂR���ق��܂��B
�E�E�E���̂ő��l�������������ꍇ�ɂ́A�Y�@�ɒ�߂�ꂽ�����Y�E�ŌY�E�����Y�ɏ�������B�܂��A���Ƌ��^�]����C�тщ^�]�A�R�O�L���i�������H�͂S�O�L���j����X�s�[�h�ᔽ�ȂǓ��H��ʖ@�Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ́A�����Y�E�ŌY�E�����Y�E�ȗ��ɏ�������B
�E�E�E���H��ʖ@�Ɉᔽ���Ă���ꍇ�ɂ́A�^�]�҂Ɉᔽ�_�����ۂ����āA�_�������ȏ�ɂȂ�ƁA�Ƌ��̒�~��������Ȃǂ̏�������B
�E�E�E���̂ő��l�������������ꍇ�ɂ́A�����ԑ��Q�����ۏ�@�i�����@�j����сA���@�V�O�X���̕s�@�s�אӔC�Ɋ�Â��đ��Q�����ӔC���B
�@�Y���ӔC�ɂ��Ăł����A���Q�҂͋Ɩ���ߎ��v�����Ō�������Ă��A���̂قƂ�ǂ����ޑ����Ƃ����������ł���A�ߕ߁E��������邱�Ƃ͂܂�����܂���B���Q�҂����ޑ��������ƁA���x�͌��@�������Q�҂��Y�������Ƃ��ċN�i���邩�ǂ��������肵�܂����A��ʎ��̂ŋN�i�����͔̂N�ԂP�O���قǂŁA�����̉��Q�҂͋N�i�P�\�����Ƃ��ĕs�N�i�ɏI����Ă��܂��B�܂��A���ɋN�i����Ă��������߁i�������J�����ɏ��ʂ̐R���݂̂łT�O���~�ȉ��̔����������n�����j�ŏI��邱�Ƃ��قƂ�ǂŁA�����Ȍ����ɂ���Ē����Y��ŌY�������n����A���s�P�\�������Ɏ��ۂɌY�����ɓ�����Q�҂͖{���ɏ��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@
���Q�҂̌Y�������́A��Q�҂̗\�z�ɔ����A�����y�����̂ŏI��邱�Ƃ��قƂ�ǂł����A���Q�҂̌Y����̐ӔC�Ɩ�����̐ӔC�Ƃ́A���ڂɊ֘A���Ă��܂��̂ŁA��Q�҂́A���Q�҂̌Y���������͂��߁A�s�������ɂ��Ă��S�������Ă����K�v������܂��B
| ���Q�҂̏����Ȃǂɂ��ẮA�ǂ�����Ēm�邱�Ƃ��ł���H |
�E�E�E��Q�Ғʒm���x�Ƃ́A��Q�҂����@���ɑ��A���Q�҂̌Y���������ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂���₢���킹�邱�Ƃ��ł��鐧�x�ł��B�₢���킹�邱�Ƃɂ���āA���Q�҂�����̎��̂̌Y���ӔC�ɂ��ċN�i���ꂽ�̂��A�܂��N�i���ꂽ�ꍇ�A�����͂��Ȃ̂��A�ǂ̂悤�ɏ������ꂽ�̂��Ȃǂɂ��ĕ������Ƃ��ł��܂��B
��̓I�ɂ́A
�P�D�����̏������ʁi���������E���������E�s�N�i�j
�Q�D�ٔ����s���ٔ����y�эٔ����s�����
�R�D�ٔ�����
�S�D��^�ҁE�퍐�l�̐g���̏A�N�i�����A�s�N�i�̗��R�̊T�v�Ȃ�
�T�D��Y�҂̌v�̎��s�\��I���\�莞���A���o�����͎��R�Y�̎��s�I���ɂ��ߕ��y�юߕ��N�����Ƃ��������Ƃɂ��Ăł��B
�@�����A�����̐����Ȃǂ���ʒm�����Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�܂��͌��@���ɖ₢���킹�����Ă݂Ă��������B���������Q�҂��s�N�i�ɂȂ��Ă��āA��Q�҂����̏����ɔ[�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A���@�R����Ƃ����Ƃ���ɉ��Q�҂̋N�i���ēx��������悤�\�������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�܂����Q�҂̍s�������ɂ��Ă��x�@�ɖ₢���킹��Δ�Q�҂͒m�邱�Ƃ��ł��܂��B��̓I�ɂ́A�Ƌ��̎�������Ƌ���~�A�_���]���A�����̏������s���Ȃ������ꍇ�ɂ͂��̎|�A�ߋ��ɉ��Q�҂��Ƌ��̎�������Ƌ���~�Ȃǂ̏���������āA�ݐϓ_�������_�ł������̂��ɂ��Ăł��B�i���������Q�҂��ߋ��ɉۂ���ꂽ�s�������ɂ��ẮA���̎��̓��e�Ȃǂ͌��J���Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�j
�@�ߎ����E�Ƃ͕����������ƁA������̑�����ւ̑��Q�����ɂ����āA�����ɔ����������Q�z�̂����A�����̉ߎ����ɑ���������z�ɂ��ẮA����Ɏx�����𐿋����邱�Ƃ��ł����A�܂��t�ɁA����ɔ����������Q�z�̂����A�����̉ߎ����ɑ���������z�ɂ��Ă͑���Ɏx���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����W�̂��Ƃ������܂��B
�@�Ⴆ�A���Q��A�̑��Q�z�P�O�O���~�i�����ԉ^�]�A�P�K�͂Ȃ��j�Ɣ�Q��B�̑��Q�z�T�O�O�O���~�i���s�ҁA���̂ɂ���Č���Q�����j�Ƃ������̂ŁAA�̉ߎ��������W�O���AB�̉ߎ��������Q�O���ł������Ƃ��܂��B
�@���̏ꍇA�́AA�̑��Q�z�̂����W�O���i�W�O���~�j��A�̉ߎ��ɂ���Ĕ����������z�ł��邽��B�ɐ������邱�Ƃ��ł����A�Q�O���i�Q�O���~�j�̂ݐ����ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����Q�҂ł���B���AB�̑��Q�z�̂����Q�O���i�P�O�O�O���~�j��B�̉ߎ��ɂ���Ĕ����������z�ł��邽��A�ɐ������邱�Ƃ��ł����A�W�O���i�S�O�O�O���~�j�̂ݐ����ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�ȏォ��AA��B�ɑ��Q�O���~�𐿋����AB��A�ɂS�O�O�O���~�𐿋����邱�ƂɂȂ�A���lj��Q��A����Q�҂ł���B�ɑ��ĂR�X�W�O���~���x�������ƂɂȂ�܂��B
�@���āA�������̃P�[�X�ŁA�ߎ������Ɋւ��Ď����Ƃ͈�����F�肪�Ȃ���A�ߎ�������A�Q�O���AB�W�O���Ƃ���Ă��܂����ꍇ�ɂ͂ǂ��Ȃ�̂��E�E�E�Ƃ������Ƃł����A�������@�Ōv�Z���Ă݂�ƁAA��B�ɑ��Đ����ł�����z�́A�W�O���~�AB��A�ɐ����ł�����z���P�O�O�O���~�ƂȂ�A���ǔ�Q�҂ł���B��A�ɐ����ł���̂͂X�Q�O���~�ƂȂ�킯�ł��B
�@����ɁAB�̉ߎ����P�O�O���ł���Ƃ��ꂽ�ꍇ�ɂ́E�E�E��Q��B��A�ɑ��P�K���������邱�Ƃ��ł����A�t��A�ɔ����������Q�̂P�O�O���i�P�O�O���~�j���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�ߎ������̖��́A���Q�����Ƃ������ʂɂ����Ă��傫�ȈӖ��������܂��B
�@�ߎ������́A���̌�̏A���̓����҂̌������A�ڌ��҂̏،��Ȃǂ��Q�l�ɁA�ǂ���ɂǂ̂��炢���̔����ɑ��Ẳߎ����������̂��Ƃ������f������킯�ł����A���Ƃ��A�ԓ��m�̎��̂̏ꍇ�A�P�O�O�F�O�̉ߎ������ɂȂ�̂́A����̃Z���^�[���C���I�[�o�[�ɂ�鐳�ʏՓ˂�Ǔˎ��̂̏ꍇ�ȂǂɌ����A����ȊO�̎��̂ł́A�q�ϓI�ɂ݂Ĕ������Ȃ��悤�Ȏ��̂ł����Ă��A�ߎ������͂P�O�O�F�O�ɂ͂Ȃ炸�A�P�O�����x�͉ߎ������蓖�Ă���Ƃ����̂���ʓI�ł��B
�@���̉ߎ������A���̂̓����҂����̂̔����ɂ��Ď��̌���ŏ،��ł���ꍇ�ɂ́A���݂��Ɍ��������咣�ł���킯�ł�����A�����A���肪���̔����ɂ��č��{�I�ȉR���������Ƃ�����A��Q�҂͂���ɑ����_���Ă������Ƃ��\�ł��B�ł�����A�ǂ��炩���ɒ[�ɑ傫�ȉR�����Ƃ������Ƃ͂��܂肠��܂���B���Ȃ͎̂��̌��Q�҂��~�}�Ԃŕa�@�ɔ�������Ă��܂��A���_�ł��Ȃ��ꍇ�ł��B���������Ƃ��ɋN���肪���Ȃ̂��A���̌�̉��Q�҂̈���I�Ȍ������݂̂���l�������Ă��܂��A���Q�҂ɗL���ȕ����֎������˂��Ȃ����Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B
�@���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����߂ɂ́A��Q�҂܂��͔�Q�҂̉Ƒ��́A���̂��ǂ̂悤�ɋN�������̂��ɂ��āA�Ǝ��ɂł��邩���蒲�ׁA�����ɔ����邱�Ƃ��،����ꂽ��A����ɑ��Ĕ��_�ł��鏀���𐮂��Ă����Ƌ��ɁA���̂̈�ʓI�ȉߎ������ɂ��Ă��c�����Ă����K�v������܂��B
�@�܂��A�ی���Ђɂ���Ă͎��̏̒������낭�ɂ��Ȃ��Łu���̎��̂̏ꍇ�̉ߎ������́����ƌ��܂��Ă��܂��B�v�u�ǂ�Ȏ��̂ł����Ă��n���h���������Ă������A��Q�҂ɂ��ߎ�������E�E�E�B�v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă邭���Ƃ�����܂��B
�@�ߎ������̖��́A�ŏI�I�ɔ�Q�҂���鑹�Q�����z��傫�����E���邽�߂ɁA�ی���Ђ��炷��A��Q�҂ɂ�����傫�ȑ��Q�������Ă��Ă��A�ߎ�������Q�҂ɉ����t���邱�Ƃ��ł���A��Ђ��x�������z�������ƌ���̂ŁA�����ɂȂ��Ă���Ƃ�������ł��傤�B
�@
���̈Ӗ��ł���Q�҂́A�ߎ������ɂ��Ď��O�ɂ�����x�̔��f�ޗ��������Ă����K�v������܂��B
�@
�@ �ȉ��͔�����x�[�X�ɂ������̌`�ԕʂ̊�{�I�ȉߎ��������f�ڂ��Ă���܂��B�ߎ������ɂ��āA�����悻�̖ڈ���m���ł̎Q�l�ɂ��Ă��������B
�@�����ł́A���̌`�ԕʂ̊�{�I�ȉߎ��������f�ڂ��Ă����܂��̂ŁA���̌`�ԕʂ̉ߎ������ɂ��āA�����悻�̖ڈ���m���Ă����Ă��������B
�@���ǂ��c�鎖�̂̏ꍇ�́A�����F��̐���ɂ��Ă̌�������X�^�[�g�ƂȂ�܂��B�����Ŕ�Y���Ƃ���Ă���ꍇ���A�����_�ł̓����Ɉًc��\�����Ă�ꍇ���A���ʐR���Ƃ��������ӂ̓��F�܂�����ŁA�ǂ̂悤�ȏ��ނ��o���ׂ�����T�d�Ɍ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���Q�����Ƃ����_�ł́A���R�̂��ƂȂ���A���̓����������ŔF�肳��邩�ǂ����ŁA���z�͑傫���قȂ��Ă��܂��B
�@���ǂ��c��ꍇ�ɂ́A��Q�҂͌������Ƃ��āA����̎����ɉe�����o�Ă��邱�ƂقƂ�ǂł���A���ɂ��̕����́A�편���v�E���Ǖ��̈Ԏӗ����ł�����Ɣ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�������A ���̓_�Ɋւ��ẮA���z���傫�������ɁA�����������藧�Ă��g���āA���z�������悤�Ƃ��Ă��܂��B����ɑ��āA��Q�ґ�������̎咣���ᖡ������ŁA�����̂��锽�_�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���ǂ��c�鎖�̂̏ꍇ�ɂ́A�����̔F��Ɋւ��邱�ƁA�܂��A���̑��Q�z�̎Z��Ɋւ��邱�ƂȂǁA������ʂŐ��I�Ȓm�����K�v�ł���A�܂��A���Ɣ�p�i�s�����m��V�E�ٌ�m��V�j���x�����Ă��A���Ƃ𗧂Ă邱�Ƃɂ���ċ��z���啝�ɑ��z����P�[�X���قƂ�ǂł��̂ŁA���Ƃɂ��T�|�[�g�͕K�{�ł���ƍl���܂��B
�@
�@�������Ȃ���A �ʏ�A���ǂ��c�鎖�̂̔�Q�҂́A�����ɓn����ʉ@��]�V�Ȃ�����Ă��邽�߁A�������������Ȃ��Ă���P�[�X�������A�܂��A���Ô�Ŏ����ӂ̌��x�z�͎g���ʂ����Ă��邽�߁A�����ӂɑ��鏝�Q���̐������s���āA�������Ƃւ̒�����ɂ��Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����P�[�X���قƂ�ǂł��B
�@�������������Ƃ���A���ɂ́A���Ƃɑ��钅������x�����Ȃ����߂ɁA�d���Ȃ�������߂Ă��܂����Ƃ�����Q�҂�����悤�ł����A���Ƃɂ���ẮA���̓_���l�����Ď�C���Ă����ꍇ������܂��̂ŁA�܂��͌�������������ŁA���k���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B���̍ۂɂ́A��C�̉ۂƋ��ɁA�����܂ł̗���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ������Ƃ�������Ɗm�F���A���̊Ԃɂ������p���͂����莦���Ă��炤�悤�ɂ��Ă��������B
�u���������Ŏ�C�����ꍇ�̂����܂��ȗ���v�Ɓu�Q�l����v�́�������
|